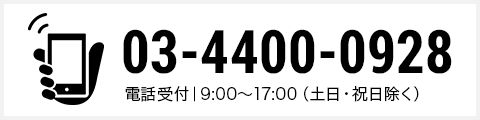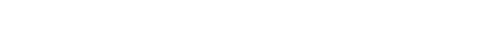Vanta × SOC2取得_インテグレーション編
~ 自動テストを活用するための実務ポイント ~
コラム「Vanta × SOC2取得:内部統制整備/エビデンス収集編」でも触れたとおり、VantaはAWS、GitHub、MDMツール、IDS/IPSツールなど、情報セキュリティに関わる各種システムと連携(インテグレーション)することで、自動テスト(Automated Test)を実行し、内部統制の有効性を検証します。
この仕組みはVantaの大きな強みですが、インテグレーションの設計や運用を誤ると、かえって作業が煩雑になったり、監査対応で混乱を招く原因となります。そこで今回は、Vantaのインテグレーション機能を最大限に活かすための実務上のポイントについて解説します。
■ インテグレーション範囲は「過不足なく」が原則
まず重要なのは、インテグレーションするツールや対象範囲を適切に選定することです。
- 範囲が広すぎる場合:SOC2検証上必要のないシステムや環境まで対象に含めてしまうと、自動テストの結果として膨大な改善要求が表示され、対応負荷が増大します。
- 範囲が狭すぎる場合:逆に、SOC2の対象となる統制項目が十分にカバーされておらず、後から監査法人からの指摘や追加要求が発生する可能性があります。
特に注意したいのは、最初にインテグレーションした段階で「全体の設計」が定まっていないと、その後のテスト結果の解釈や対応に手間取るという点です。
■ 自動テストの対象と除外(deactivate)の考え方
ツールとのインテグレーションが完了すると、Vantaは自動的に全システムをスキャンし、設定されたルールに基づいて各統制項目のテストを実施します。たとえば、AWSを連携した場合、次のような構成要素がすべてテスト対象になります:
- EC2
- DynamoDB
- CloudWatch Log Groups
- ECR(コンテナ)
- IAMポリシー/ユーザー
- ALB(Application Load Balancer) など
その結果、Vantaのダッシュボード上には、各コントロールの基準に充足していない箇所や改善が必要と判断された項目が一覧で表示されます。
ここで重要なのが、すべてを実際に改善しなければならないわけではないという点です。中には以下のような理由でテスト対象から除外(deactivate)すべきものもあります:
- ステージング・開発環境:本番環境以外はSOC2の対象外となるため、除外対象とするのが一般的です。
- 誤検知や特殊な運用上の理由:システム設定上問題がないにもかかわらずエラーと判断される場合や、要件に合致しないが補完統制が十分備わっている場合等、合理的な説明があれば除外可能です。
除外する場合は「合理的な説明」と「監査法人とのすり合わせ」がカギ
ただし、テスト対象から除外(deactivate)した内容やその判断の妥当性は、監査法人の確認対象になります。除外の根拠や背景を適切に説明できなければ、監査時に再対応を求められる可能性があります。
したがって、以下のような対応を取ることが望ましいでしょう:
- 除外の前に社内で十分に理由とリスク評価を整理する
- 必要に応じて監査法人と事前に相談・合意形成を行う
- 除外理由をVanta上にも記録しておく(説明責任の明確化)
インテグレーションの設計段階から、監査法人と密に連携し、期待されるコントロールの適用範囲や、除外の許容度について視点合わせを行っておくことで、後工程での修正や混乱を最小限に抑えることができます。
■ まとめ
Vantaの自動テスト機能は、効率を高める一方で、適切なインテグレーション設計と除外判断の運用が求められます。
- 過不足のないインテグレーション設計を行う
- 除外判断には合理的根拠を用意し、必要に応じて監査法人と合意を取る
- 自動テストの結果を鵜呑みにせず、自社の実態と照らして対応方針を判断する
このような運用ができれば、Vantaを最大限活用しつつ、無駄なく確実にSOC2レポートの取得を目指すことが可能です。